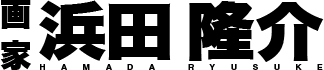
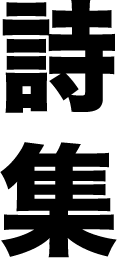
四十才になった年の冬、周りの反対や説諭を無視して、私は家族を引連れ琵琶湖の西化、舟木という土地に移り住んだことについて特に取り立てて云う程の理由もなかったし、生活への危惧も全くなかった。
宿り木生活にいささか嫌気がさしたことがキッカケになったことは否めない。
移り化む場所は何処でもよかったわけで、親戚縁者、友人、知人に迷惑承知で強引に下手糞な絵を売りつけて、そのお金を全部バラの苗木に変え、無償で借りた荒地の開蠻を始めた。
半ば廃屋の百姓家に月千円の家賃を払い、熟年人生を自然とアートに埋没させてしまおうとしたのである。
二十年振りかの洪水で川原に植えた私の財産は、一年目の花の収穫を待たずそっくり湖に流れ去ってしまった。
生活を続ける為に、またぞろ街に出て、血みどろの闘いをすることになるのだが、どう云う理由か、お金のかかるゴルフというスポーツ(?)を覚える羽目にもなった。ゴルフというスポーツは平均的に誰もが熱病のように狂い猛ける時期を持つものらしい。
私も八月の炎天下に三日間毎日二ラウンドプレイを続けた経験を苦々しい想いでとして残している。
“たかがゴルフ、されどゴルフ”という名文句を聞くが“されど”に拘り勝ちなのが一般的素人ゴルファーの人情らしい。“たかが”の側から云えば、せいぜい写真やイラスト入りでもたかだかA4判二百頁位の紙面に纏めてしまえる内容のものを、月刊、週刊、日刊の刊行物に手を変え品をかえて、繰り返し活字にする行為を、よくぞまあと半ば呆れ、軽蔑の目で見流しながらも、多少は気にして、切磋琢磨の練習効果を理念としては認めても、情念として認めたがらず、コースでの僥倖を祈る心情を自己の技術的実力と自信に結びつける幻想に酔い、“ゴルフは所證メンタルでありイメージのスホーツだわさ”と嘯きながら、場に臨んで、気負いと力みでポカを続けて奈落に落ちる結果をたかがゴルフと自らを慰め、次への期待の驕ぶりの必地良さにニタリとするどうしようもないリベラルゴ ルファーに、天の声は“汝禅寺へ行きやれ” と宣う。 百科辞典で“禅”を引いてみた。一気に解読するにはいささかシンドイぐらいの解説が載っていた。
禅は瞑想であり、原語dhyanaは静かに物事を考えるという意味であるらしいのである。
物事は多種多様で、めいめいがどの方向から、何をどのように考えようと、ただ静かに考えればいいのであって、考えれば考える程疲れ、汚れなき知恵の光明が各々の日常生活の上に輝き、次回の精神と既成文化の領域を超えたグローバルな近代的野垂れ死哲学の自在さを見出せると書いてはないが私は勝手にそう解釈した。
私は次のコンペには必ず優勝と心に決め、練習には行かないが心は秘かにセッセと禅寺通いをしている。
(昭和六〇年五月二六日)
