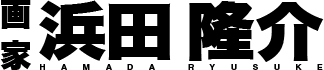
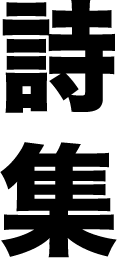
“生産性”いうGODが釈迦・キリストに代って頭角を現わしてきたのはー七六〇~一八三〇・四〇年にイギリスで興った「産業革命」といわれた、技術的•経営的、かつ社会的な変革の波に押し上げられたものと理解する。
この風潮が国際的規模に発展して、当時の日本という特種な民族的•国家的な反抗も全然通用しなかった。
この偉大なるGODが人間性を画一化する社会制度を作っていく過程の中で近代文化が多様化していくのは当然である。
経済の論理が民族的個性を風化させていく現象を、規制の中で個の絶対自由を確立しようとする宗教や芸術の感性に通じる自己規制精神を、一見没個性派知識階級に見ることができる。
サイエンスはわれら人間が培養したゴキブリ的存在とすれば、サイエンスを積極的に肯定しながら何となくツッパリを見せ、社会制度の制約内に、より狭義に自らを絞めあげて没個性の原理を押し出そうとして、時折棘を出す自虐的自由平等博愛主義者達をディレッタントと呼べるのかも知れない。
俳諧とは、おどけ、たわむれ、潛稽の意があり、発句俳譜連歌の初句、頭句で、独立して俳句は七五七で言い切りの句である。
絶句とは漢詩の近体詩の一つであり、起・承・転・結の四句からなり、五言と七言がある。唐初に起こり唐代に盛行して古体詩と対決する。
そこで次の七言絶句
空 鉦 轟 音 成レ 鯨 皮
魅レ 雅 都 妓 夥 多レ 能
好 師 落 照 余レ 丈 榛
(昭和五八年五月五日はこどもの日・六五才)