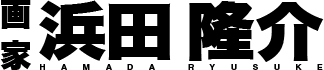
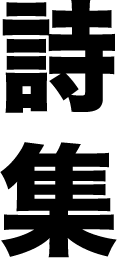
私と“菊三”との出会いは、熱帯夜の異状に続いた夏の盛りも漸く終り、二百二十日前後の夜だっと思います。
それでも宵のうちは、窓をすっかり開け放しておいてもまだ扇風機の邪魔にならない程の暑さが残っていたようでした。
絵を描くために寄寓しているS君の部屋があるマンションの三階は、椅子机の置かれている東側の窓の下と、隣の家の屋根庇がほぼ同じ高さで三〇糎足らずの隙間をおいて隣接しています。
昼はオレンヂ色がかった西洋風の巧配が尽きる尾根の向うに、をのまた隣りの建物のヒビ割れたモルタル壁が頭を出し、屋上の物干場には、雨の日以外、サイケデリックな満艦飾が観賞できるといった光景です。
“菊三との出会い”の詳しい時間は覚えていませんが、電気スタンドの明かりの中に、薄闇に埋没した瓦屋根の匈配を背にキチンと正座して、じっと私を見詰めている一匹の猫に気付いたとき、何故か私は少年の“胸のときめき”をおぼえました。
何時間も前から坐っていたのか、数分前にやって来たのか、これから始まる田舍芝居の口上語りを勤める太夫よろしく神妙でした。
私の凝視がキッカケとおぼえてかおもむろに立ちあがり、丸く背中を持ち上げて、ニャーオと一声鳴くと、私の居る方へ二歩三歩と音もなく近寄って来ました。
“チョッ、チョッ”と私が舌を鳴らすと、もうひと声「ニャーオ」と鳴いて前肢を窓枠に掛けて軀をのり出し、首を左右に廻して部屋の中を胡散気に伺うと、いきなりヒョイと机の上に跳び上り、また「ニャーオ」と鳴きました。
“太夫只今参上”といった態で、舞台七・三の見得をきったっもりでしよう。
人間でいうと中学三年生の年恰好の雄で、まだ少し仔猫の乳臭さが抜けきらず、白、黒、茶が縞、班、絞りに茫洋と混り合った軀がかなり汚れていました。
ふた昔にもなりますが、私が家族と共に琵琶湖の北西に移り住み、廃屋を借りて芸術と貧乏と自然との対話に熟年の青春を賭けていた頃、わが家には家族五人の他に犬三匹と猫が八匹から一〇匹ぐらい同居していました。
犬は友人知人からもらいうけた素性のいいものばかり(エヤデール•ダックスフンド•スピッツ)でしたが猫の方は子供達が拾い集めてきた捨猫ばかりです。
子供達の動物好きが隣近所に知れ渡り、遊び仲間が捨て猫の場所を注進に来たり、わざわざ家の前まで運んで呉たりして、このままでいくとわが家は動物と共に餓死必中を為なくてはと真面目に思ったこともありました。
よくしたもので、猫という小動物の習性は、犬と違って、人間に飼馴らされることを嫌うようです。
犬は人間じ飼育されることを目的としているようなところがあるように思われるのですが、猫は何処か反抗的な行動が目立って、同居している人間の営む生活環境を批判的に見ることができる本能があるようです。
半ばキャンプ生活のような關放的環境に野性化していくのか、貧乏人の子沢山がもたらす分配供給のキャパシティを計算してのことか、三匹拾ってくると二匹が何時のまにか姿をかくすという。パターンで我が家の経済的潰滅を救ってくれました。
突然闖入してきたお芝居がかりの少年猫も、おそらくは以前居た“環境”の悪さに愛想を尽かして家出をしてきたとしても、なぜ私たちの部屋を狙ったのかが疑問です。
S君が“菊三”と名ずけました。
(昭和五八年一〇月一二日・田中角栄判決の日)